Zendesk vs Intercom:AI自動返信機能の徹底比較とビジネスを加速する活用術

顧客対応の現場でAIの活用が急速に進んでおり、カスタマーサポートの効率と品質は飛躍的に向上しています。しかし、「AI自動返信」と聞いても、具体的にどのように業務が改善されるのか、初心者の方にはイメージしにくいかもしれません。この記事では、カスタマーサポートツールとして広く知られるZendeskとIntercomのAI自動返信機能に焦点を当て、現場で今すぐ使える文面作成のコツからツールの比較まで、専門用語を避けながら分かりやすく解説します。
本記事を通じて、以下のポイントを理解し、あなたのビジネスにおける顧客対応を一段階レベルアップさせるヒントを得ることができます。
- NG表現の回避術:お客様に不快感を与えない言葉選びと、その具体的な改善例。
- 心を動かす謝罪の構成:クレーム対応に不可欠な、信頼を回復するための謝罪メールの書き方。
- 次の一手を明確に:問い合わせ対応をスムーズに終結させるための、次に行うべきアクションの示し方。
- SLAに応じた対応の違い:サービスの品質基準(SLA)に合わせた、最適な返信スタイルの使い分け。
- Zendesk vs Intercom徹底比較:両ツールのAIテンプレート作成支援機能の特徴と、どちらが自社に適しているかの判断基準。
- 品質を均一化するテンプレート設計:チーム全体の対応品質のばらつきをなくし、一貫したトーンを保つ方法。
初心者や一般的なビジネスパーソンの方でもすぐに実践できるよう、図表や具体例を豊富に交えながら、実践的な知識を丁寧にお伝えします。それでは、さっそく見ていきましょう。
1. NG表現を撲滅!顧客満足度を高める言葉遣いと改善テクニック
「NG表現」とは、その名の通り「使うべきではない表現」や「避けるべき言い回し」を指します。カスタマーサポートの現場では、意図せずお客様を不快にさせたり、誤解を招いたりする言葉遣いを避けるため、NGワードをリストアップしておくことが非常に重要です。ここでは、典型的なNG表現とその改善例を紹介し、誰が対応しても高品質な顧客体験を提供するための基礎を学びます。
やってはいけないNG表現の具体例
顧客の不満を増幅させてしまう代表的なNG表現には、以下のようなものがあります。これらは、相手を突き放すような、一方的で冷たい印象を与えがちです。
- 「できません」「無理です」:お客様の要望を真っ向から否定する、最も避けたい表現です。
- 「規則なので」「社内のルールです」:会社側の都合を押し付け、お客様の状況に寄り添っていない印象を与えます。
- 「落ち度はありません」:クレームに対して自社の非を一切認めない態度は、火に油を注ぐことになりかねません。
- 「誤解されています」:「あなたの理解が間違っている」と、相手を責めているように聞こえてしまいます。
これらの表現は、お客様との間に壁を作り、問題解決から遠ざけてしまう危険性を持っています。
ポジティブな言い換えで信頼を築く方法
NG表現を避けるだけでなく、それをポジティブで柔軟な表現に置き換えることが、顧客との良好な関係を築く鍵となります。クッション言葉を効果的に使い、代替案を提示する姿勢が大切です。
| NG表現 | 改善例 | ポイント |
|---|---|---|
| できません / 無理です | 「あいにくご要望には沿いかねますが、代替案として〇〇はいかがでしょうか?」 | ただ断るのではなく、代替案を提示することで、解決に向けて協力する姿勢を示します。 |
| 規則なので… | 「規約上、難しい点ではございますが、その範囲内で私どもにできることをご案内いたします。」 | 規則の背景に触れつつも、顧客に寄り添い、可能な限りのサポートを約束します。 |
| 誤解されています | 「私の説明が至らなかったかもしれません。改めてご説明いたしますと…」 | 相手の理解力のせいにするのではなく、自身の説明不足を認め、丁寧に説明し直す謙虚な姿勢が重要です。 |
また、「〇〇してください」といった命令形も、「お手数ですが、〇〇いただけますでしょうか?」のような依頼形に変えるだけで、お客様に与える印象は格段に柔らかくなります。こうした小さな配慮の積み重ねが、顧客満足度の向上に直結するのです。
2. クレームをチャンスに変える!信頼を回復する謝罪文の基本構成
ミスやトラブルが発生した際の謝罪は、顧客の信頼を取り戻すための最も重要なステップです。しかし、ただ謝るだけでは不十分。効果的な謝罪文には、相手の感情に寄り添い、誠意を伝えるための「型」があります。ここでは、初心者でもすぐに実践できる謝罪文の基本構成と、そのまま使えるテンプレートをご紹介します。
心を動かす謝罪文の5ステップ
ビジネスシーンにおける効果的な謝罪メールは、以下の5つの要素で構成するのが基本です。この流れを意識することで、誠実さが伝わりやすくなります。
- 冒頭での率直な謝罪:時候の挨拶などは省略し、「この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と、まずはお詫びの言葉を述べます。
- 事実の確認と共感:何に対して迷惑をかけたのかを具体的に示し、「さぞご不快な思いをされたことと存じます」と、相手の気持ちに寄り添う一文を加えます。
- 原因の簡潔な説明:言い訳がましくならないよう注意しながら、「社内の連携ミスにより…」など、原因を簡潔に説明します。
- 具体的な解決策と再発防止策の提示:「本日中に代替品を発送いたします」といった具体的な対応策と、「今後はチェック体制を強化し…」という再発防止への取り組みを明確に伝えます。
- 結びでの再度のお詫び:最後に改めて、「重ねてお詫び申し上げます」と謝罪の言葉で締めくくります。
この「謝罪 → 共感 → 原因説明 → 解決策 → 再度の謝罪」という流れが、相手の怒りを鎮め、信頼回復への道を開きます。
【コピペOK】そのまま使える謝罪メールテンプレート
以下に、上記の構成に沿った謝罪メールの文例を示します。状況に応じて内容を調整してご活用ください。
件名:【株式会社〇〇】お問い合わせいただいた件に関するお詫び 株式会社△△ △△部 △△ △△様 いつもお世話になっております。 株式会社〇〇の〇〇です。 この度は、弊社の不手際により△△様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。 お問い合わせいただいた「〇〇」に関しまして、本来の納期に間に合わず、ご心配をおかけし大変申し訳ございませんでした。 原因を調査しましたところ、弊社内の確認プロセスに遅延が生じていたことが判明いたしました。 現在は社内体制を見直し、同様の事態が再発せぬよう、再発防止に努めております。 つきましては、〇〇の件、本日中に必ず完了させ、改めてご連絡を差し上げます。 今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。 この度の件では、△△様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。 何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 ----------------------------------- 株式会社〇〇 〇〇部 〇〇 〇〇 (連絡先など) -----------------------------------
返信が遅れてしまった場合は、冒頭で「ご返信が遅くなり、大変申し訳ございません」と一言添えるだけで、お客様の印象は大きく変わります。誠意ある対応を心がけましょう。

3. 顧客を迷わせない!「次の一手」を明確に示す方法
問い合わせ対応において、単に質問に答えるだけでなく、「次に何をすればよいか」を明確に示すことは、顧客の不安を取り除き、満足度を高める上で非常に重要です。この「次の一手」を効果的に提示することで、やり取りがスムーズに進み、不要な再問い合わせを防ぐことができます。
例えば、問題解決までにもう少し時間が必要な場合、「この後、担当部署にて詳細を確認し、明日15時までに改めて進捗をご連絡いたします」と具体的な期限を伝えるだけで、お客様は安心して待つことができます。放置されているという不安を抱かせないことが肝心です。
効果的な言い回しのポイントは、ここでも「命令」ではなく「提案・案内」の形を取ることです。「〇〇してください」ではなく、「次のステップとしまして、〇〇をご入力いただけますでしょうか?」のように、柔らかい表現を心がけましょう。
さらに、サポート側がアクションを起こしたことを伝える際には、「ただいま返金処理を行いました。3〜5営業日以内に口座に反映される見込みです」のように、過去形や進行形を使って迅速な対応をアピールすると、お客様の安心感は一層高まります。最後に「もし、うまくいかない場合は、再度お気軽にご連絡ください」と付け加えることで、最後まで寄り添う姿勢を示すことができます。
4. SLA(サービスレベル合意)に応じた最適な応答スタイル
SLA(Service Level Agreement)とは、サービス提供者が顧客に対して保証するサービスの品質レベルを定めたものです。カスタマーサポートでは、「問い合わせに24時間以内に返信する」といった応答時間がSLAとして定められていることが多く、これを遵守することは企業の信頼性を保つ上で不可欠です。
では、SLAで定められた時間によって、どのように応答スタイルを変えるべきでしょうか。
「即時対応」が求められる場合(例:1時間以内)
チャットサポートなど、迅速さが最優先される場面では、簡潔で要点を押さえたコミュニケーションが求められます。長い挨拶は省き、まずはお客様の問題解決に直結する回答から始めましょう。この時、ZendeskやIntercomが提供する定型文(マクロ)やショートカット機能を活用すると、スピードと丁寧さを両立できます。
また、すぐに完全な回答ができない場合でも、「お問い合わせありがとうございます。ただいま詳細を確認しておりますので、5分ほどお待ちいただけますでしょうか」といった「一次回答」を送ることで、お客様は無視されていないと感じ、安心して待つことができます。
「48時間以内」など、時間に猶予がある場合
メールでの問い合わせなど、対応時間に比較的余裕がある場合は、スピードよりも内容の充実度が重視されます。まず、問い合わせを受け付けた時点で「お問い合わせを受け付けました。担当者より48時間以内にご返信いたします」といった自動返信メールを送ることで、お客様は「無事に届いたか」という不安から解放されます。
実際の返信では、経緯や解決策を丁寧に説明し、箇条書きや段落分けを工夫して読みやすい文章を心がけましょう。また、お待たせしたことに対して「返信が遅くなり申し訳ございません。お待ちいただき、ありがとうございました」といった感謝とお詫びの一言を添える配慮が、丁寧な印象を与えます。
5. Zendesk vs Intercom AI返信支援機能の徹底比較
ここからは、この記事の核心であるZendeskとIntercomのAI機能を比較していきます。どちらのツールも強力なAIアシスタントを備えていますが、そのアプローチには違いがあります。自社のニーズに合ったツールを選ぶための参考にしてください。
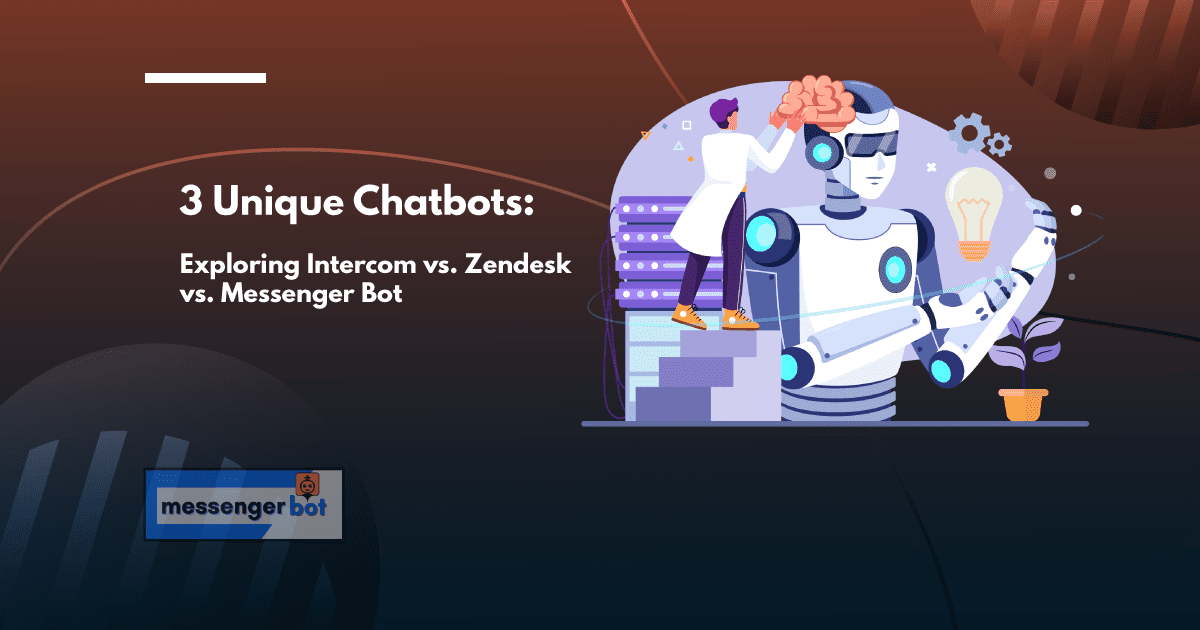
Zendesk AI (Copilot):既存サポート業務への強力なアドオン
ZendeskのAI機能「Zendesk Copilot」は、主にサポート担当者(エージェント)の業務を効率化することに主眼を置いています。その特徴は以下の通りです。
- 返信文の自動生成:問い合わせ内容をAIが解析し、社内のナレッジベースや過去の対応履歴から最適な返信文のドラフトを自動で作成します。担当者はそれを確認・修正するだけで済むため、返信作成時間が大幅に短縮されます。
- 文章トーンの自動調整:ワンクリックで文章をより丁寧にしたり、逆に簡潔にしたりと、状況に応じたトーンに自動で変換してくれます。これにより、誰が書いてもブランドイメージに合った文体を保つことができます。
- AIボットとの連携:簡単な質問はAIボットが自動で回答し、複雑な問題のみを人間の担当者に引き継ぐことで、サポート全体の効率を最大化します。
Zendeskは、既存のチケット管理システムをベースに、AIの力で担当者のパフォーマンスを向上させるというアプローチを取っています。
Intercom (Fin AI):会話体験全体に溶け込むAI
一方、IntercomのAI「Fin」は、顧客とのコミュニケーション体験全体を向上させることを目的として設計されています。チャットを起点としたシームレスな体験が特徴です。
- 高機能なAIエージェント (Fin AI Agent):自社のFAQやヘルプ記事を学習し、顧客からの質問に人間のように自然な対話で直接回答します。回答の口調(トーン)や参照する情報の範囲を細かくカスタマイズできるため、ブランドの世界観を損ないません。
- 担当者向けアシスタント (Fin AI Copilot):担当者が対応している最中に、会話内容をリアルタイムで要約したり、関連する社内情報を提示したりと、強力なアシストを行います。これにより、引き継ぎがスムーズになったり、回答の精度が向上したりします。
- 直感的な設定:専門的な知識がなくても、比較的簡単にAIボットの設定やカスタマイズが行える点が強みとされています。
どちらを選ぶべきか?機能と価格モデルの比較
両者の違いをまとめると、以下のようになります。
| 比較項目 | Zendesk (Copilot) | Intercom (Fin AI) |
|---|---|---|
| アプローチ | サポート担当者の生産性向上を重視 | 顧客との対話体験全体の向上を重視 |
| 強み | 既存のサポートフローへの統合、返信ドラフト生成 | 高機能なAIボット、簡単なセットアップ、会話アシスト |
| 価格モデル | 担当者1人あたりの月額固定料金 | AIが解決した件数に応じた従量課金 |
メールベースのサポートが中心で、担当者の作業負荷を軽減したい場合はZendeskが、Webサイト上のチャットを起点に顧客とのエンゲージメントを高め、自己解決率を向上させたい場合はIntercomが、それぞれ有力な選択肢となるでしょう。
6. 属人化を防ぐ!対応品質を均一化するテンプレート設計法
AIツールを導入しても、その基盤となるテンプレートの品質が低かったり、チーム内で使い方がバラバラだったりすると、効果は半減してしまいます。ここでは、誰が対応しても一貫した高品質なサポートを提供するための、テンプレート設計のポイントを解説します。
トーン&マナーを統一するスタイルガイドの作成
まず、チーム全体で共有する「スタイルガイド」を作成しましょう。これには、お客様の呼び方(「お客様」「〇〇様」など)、敬語のレベル、句読点や記号(!マークなど)の使い方といった、細かいルールを定めます。これにより、「Aさんの返信は丁寧だけど、Bさんの返信は少し雑」といった属人化を防ぎ、企業としての一貫した姿勢を示すことができます。
シーン別にテンプレートを整備する
次に、よくある問い合わせのシナリオごとにテンプレートを用意します。これにより、返信作成の時間を短縮できるだけでなく、対応の漏れやミスを防ぐことができます。
- 新規問い合わせへの一次回答テンプレート
- クレームへの謝罪テンプレート
- 製品の不具合報告への返信テンプレート
- よくある質問(FAQ)への回答テンプレート
- 返信遅延のお詫びテンプレート
これらのテンプレートを整備し、チームで共有することで、新人でもベテランと同じレベルの初期対応が可能になります。
テンプレートは「育てる」もの
テンプレートは一度作ったら終わりではありません。サービス内容の変更や、お客様からの新たな質問傾向に合わせて、定期的に見直しと更新を行うことが重要です。チーム内で「この表現は分かりにくい」「もっと良い言い回しがある」といったフィードバックを収集し、常にテンプレートを最適な状態に「育てていく」意識を持ちましょう。変更があった際は、必ずチーム全員に周知徹底することも忘れないでください。
最後に、テンプレートを使いながらも、お客様一人ひとりの状況に合わせた「一言」を添えることを忘れないでください。「いつもご利用いただき、ありがとうございます」といったパーソナルな一文が、機械的な対応ではない、人間味のある温かいサポートを実現します。
おわりに
ZendeskやIntercomが提供するAI機能は、カスタマーサポートの現場にとって非常に強力な武器となります。この記事で紹介した、NG表現の回避、誠意の伝わる謝罪、明確なアクション提示といった人間ならではのコミュニケーションスキルとAIを組み合わせることで、その効果は最大化されるでしょう。
AIとテンプレートを活用することで、対応の「スピード」と「品質」という、これまで両立が難しかった課題を高いレベルで解決することが可能です。これにより、顧客満足度の向上はもちろん、サポート担当者の負担軽減にも繋がり、より創造的な業務に時間を使うことができるようになります。
本記事を参考に、まずは自社の課題に合った小さなステップから、AIの導入やテンプレートの整備を始めてみてはいかがでしょうか。顧客対応は企業の「顔」です。AIと人が賢く協働することで、これからの時代に求められる、新しいカスタマーサポートの形を築いていきましょう。


