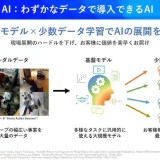HubSpotブログのトラフィック75%減!その原因とAIO時代を生き抜くSEO再構築50のチェックリスト
先日、マーケティング業界に衝撃が走りました。インバウンドマーケティングの代表格であるHubSpot(ハブスポット)のブログサイトにおけるオーガニック検索トラフィック(自然検索からの流入)が、ここ数年で約75%も減少したというニュースです。 [25, 28] SEOと優れたコンテンツで成功を収めてきたはずのHubSpotに、一体何が起きたのでしょうか。
本記事では、この劇的なトラフィック減少の背景にある要因を、初心者の方にも分かりやすく解説します。さらに、これからのAI時代に必須となる新しいウェブ最適化の考え方「AIO(Answer Engine Optimization)」、つまりAIによる「回答エンジン」にいかにして情報を届けるか、という視点から、具体的なSEO再構築タスク50項目のチェックリストを提示します。 [2, 6, 9] ご自身のサイト運営を見直すきっかけとして、ぜひご活用ください。
HubSpotブログのトラフィックはなぜ急減したのか?3つの複合的要因
結論から言うと、HubSpotブログのトラフィック急減は、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発生しました。主な背景として、以下の3点が挙げられます。
- 広範すぎるコンテンツ戦略による専門性の希薄化
- Googleのアルゴリズム更新による「質の高い専門サイト」の重視
- AIによる検索回答表示(AI Overviews)の普及によるクリック数の減少
それぞれを詳しく見ていきましょう。
1. 幅広すぎるトピック戦略の限界
HubSpotブログは、本来の事業領域であるマーケティングやセールス以外にも、「有名な名言集」や「肩をすくめる絵文字の打ち方」といった、事業との関連性が薄い非常に広範なトピックの記事を多数公開していました。 [14, 20] これらは検索される回数が多いため、一時は多くのアクセスを集める源泉となっていました。しかし、Googleは近年、サイト全体の専門性やテーマの一貫性(Topical Authority)をますます重視するようになっています。 [13, 18, 20, 26]
その結果、HubSpotの事業と直接関係のない、いわば「付け焼き刃」的なコンテンツはGoogleからの評価が下がり、検索順位が下落。これがトラフィック減少の一因となりました。 [14] 実際に、トラフィックが落ちた記事の多くがビジネスと関係の薄いトピックだった一方で、「メール分析」や「ランディングページのコツ」といった専門分野の記事は順位を維持、あるいは向上させています。 [14] この事実は、広く浅いコンテンツよりも、深く専門的なコンテンツが評価される時代へのシフトを明確に示しています。
2. Googleアルゴリズム更新と「役立つコンテンツ」の重視
HubSpotの流入減少は、2023年以降に複数回実施されたGoogleのコアアップデート、特に「ヘルプフルコンテンツアップデート(Helpful Content Update)」の時期と重なります。 [8, 10, 11] このアップデートは、「ユーザーの役に立つこと」よりも「検索エンジンで上位表示されること」を主目的に作られた、質の低いコンテンツの評価を下げるためのものです。 [8, 17, 22]
Googleは、サイト運営者に対して「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」という品質評価基準を提示しており、ユーザーにとって本当に価値のある、信頼できる情報かを厳しく見ています。 [13, 26, 29] HubSpotの場合、収益に直結する主要なキーワードの順位は維持されていたことから、Googleがサイト全体の専門性を評価し、「本業と関係の薄い部分」の評価を選択的に下げた可能性が指摘されています。 [14]
3. AIによる検索回答表示(AI Overviews)の影響
最も大きな変化として専門家が注目しているのが、Google検索結果の上部に表示されるAIによる要約回答「AI Overviews」の普及です。 [3, 7, 12, 15] これは、ユーザーが検索した質問に対し、ウェブページをわざわざ開かなくてもAIが要点をまとめて回答を提示する機能です。
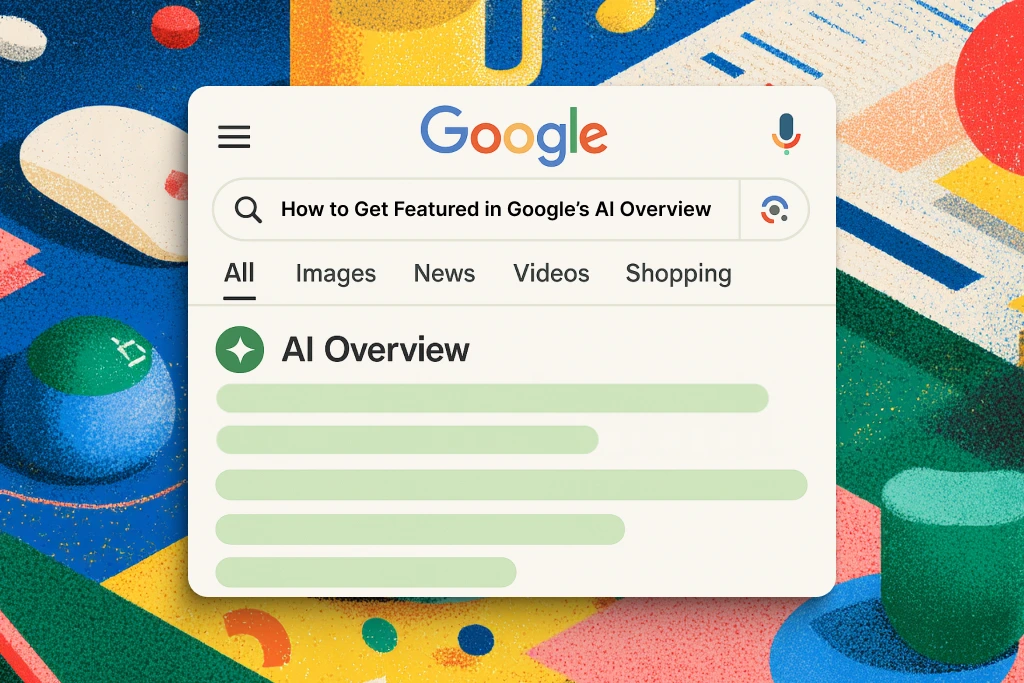
その結果、これまで検索1位のサイトに訪れて得ていた情報が、検索結果ページ上で完結してしまい、サイトへのクリックが発生しない「ゼロクリック検索」が増加しています。 [2, 21] HubSpotが得意としてきた「~とは何か」「~する方法」といった情報提供型のキーワードは、まさにAIが回答を生成しやすい領域です。ある調査では、AI要約が表示されると、表示されない場合に比べてページのクリック率が34.5%も低下するというデータも報告されています。 [7] さらに別の調査では、AI要約が表示されたページの外部リンククリック率は8%にとどまり、表示されない場合の15%からほぼ半減したとの結果も出ています。 [3, 23] HubSpotが獲得していた大量のトラフィックは、このAI回答によるクリック率低下に大きく影響されたと考えられます。
幸い、HubSpot自身もこの変化に対応し始めており、関連性の低いページを削除・整理するなど、コンテンツ戦略の見直しを進めています。 [30] この事例は、私たちサイト運営者にとっても他人事ではありません。では、この「回答エンジン」の時代に、私たちはどのようにウェブ戦略を再構築すればよいのでしょうか。
AIO(Answer Engine Optimization)時代に備える3つの基本戦略
これからの時代は、従来のSEO(検索エンジン最適化)に加え、AIO(回答エンジン最適化)という考え方が重要になります。 [1, 4, 9] これは、AIがあなたのサイトの情報を正しく理解し、回答として引用・推薦してくれるようにコンテンツを最適化することです。 [2, 31, 32, 33] 具体的に取り組むべき3つの基本戦略を紹介します。
Task 1: 回答エンジン向けにコンテンツを構造化する
AIは、整理され、構造化された情報を好んで解釈します。 [32] AIに「分かりやすい」と思ってもらうための工夫は、人間の読者にとっても親切です。
- 見出しをQ&A形式にする: ユーザーが入力しそうな「〇〇とは?」「〇〇のやり方」といった疑問をそのまま見出し(H2, H3)にし、その直下で簡潔に答える。
- 冒頭で結論を述べる: 記事の最初に、質問に対する答えや要約を提示する「結論ファースト」を徹底する。
- 箇条書きや表を活用する: 手順や特徴など、列挙できる情報は積極的にリストや表形式で整理する。
- 1ページ1テーマを徹底する: 1つの記事であれもこれもと欲張らず、1つの中心的な質問に答えることに集中する。
Task 2: FAQコンテンツを戦略的に活用する
FAQ(よくある質問)セクションは、AIOにおいて非常に強力な武器になります。AIはユーザーの質問に答える際、それに近いQ&A形式のコンテンツを引用しやすいためです。
- ユーザー視点のリアルな質問を用意する: 顧客から実際に寄せられる質問や、検索キーワードから想定される疑問をFAQに盛り込む。
- 簡潔な質問と回答を心がける: AIが抽出しやすいよう、質問も回答も長すぎず、要点をまとめたものにする。
- 構造化データを実装する: 技術的な対応が可能であれば、FAQスキーマと呼ばれる構造化データでマークアップし、Q&Aであることを検索エンジンに明確に伝える。
Task 3: クリックを促す新しいCTA(行動喚起)を設計する
AIの回答だけで満足されてしまっては、サイトへの訪問にはつながりません。AIの回答を「きっかけ」として、クリックしてもらうための工夫が必要です。
- AIに提供できない価値を提示する: テキスト情報で完結しない「無料テンプレートのダウンロード」「インタラクティブなツールの試用」「デモ動画の視聴」など、サイト訪問が必要な価値をCTAとして用意する。 [34, 35]
- コンテンツの文脈にCTAを溶け込ませる: 「より詳細な手順は、こちらの完全ガイドで解説しています」のように、文章の流れの中で自然に次のアクションを提示する。
- CTAの文言を具体的にする: 「詳しくはこちら」のような曖昧な表現ではなく、「専門家による解説動画を見る」「3分で完了する無料診断」など、得られるメリットが具体的にわかる言葉を選ぶ。 [34, 35]
AIO時代に対応するSEO再構築50の実践タスクチェックリスト
ここからは、HubSpotの事例から得られた教訓とAIOの考え方に基づき、具体的な50のタスクをチェックリスト形式で紹介します。ご自身のサイトがどこまで対応できているか、ぜひ確認してみてください。

● コンテンツ戦略の見直し(サイト全体の方向性を整える)
- コンテンツ監査の実施:全記事をリスト化し、サイトの専門性と関連が薄い記事を特定する。
- 低関連コンテンツの整理:事業との関連が薄い記事は、削除またはより関連性の高い記事へのリダイレクトを検討する。 [30]
- 重複コンテンツの統合:同じようなテーマを扱った記事が複数あれば、1つの包括的な記事に統合する(カニバリゼーション対策)。
- 情報鮮度の維持:内容が古くなった記事は、最新情報にアップデートし、更新日を明記する。
- 専門性の強化:サイト全体で一貫した専門テーマを掲げ、その分野での第一人者を目指す。 [20]
- ビジネスゴールとの連携:全てのコンテンツが、最終的に自社のビジネス目標(リード獲得、ブランディング等)にどう貢献するかを明確にする。
- 検索意図の再調査:ターゲットキーワードで現在上位表示されているサイトを分析し、ユーザーが何を求めているかを再定義する。
- ファネル全体の最適化:認知獲得(Top)だけでなく、比較検討(Middle)や購入(Bottom)段階のユーザーに向けたコンテンツを充実させる。
- 商用クエリへの注力:「〇〇 価格」「〇〇 おすすめ」のような購買意欲の高いキーワードのコンテンツを強化する。
- 独自コンテンツの企画:自社データを用いた調査レポート、独自の事例研究、専門家へのインタビューなど、AIには生成できない一次情報を作る。
● コンテンツ作成・最適化(各ページの内容と構成を改善)
- 1ページ1主質問の原則:各ページが「どの問いに答えるか」を明確にし、タイトルに含める。
- 冒頭での要約(リード文):記事の最初に結論や要点をまとめたサマリーを記載する。
- 論理的な見出し構成:H2、H3タグを使い、見出しだけで記事全体の流れが理解できる構造にする。
- 箇条書き・表の活用:手順、比較、リストなどの情報は、積極的に箇条書きや表で視覚的に整理する。
- 専門用語への配慮:専門用語や略語には、簡単な説明を添えるか、用語集ページへリンクする。
- ページ内重複の排除:1つの記事の中で、同じ説明を何度も繰り返さない。
- FAQセクションの導入:記事の最後に関連するQ&AをまとめたFAQセクションを設ける。
- FAQスキーマの実装:FAQ部分に構造化データを追加し、AIにQ&Aであることを伝える。
- オリジナル画像の活用:文章だけでは伝わりにくい情報は、図解、グラフ、スクリーンショットなどのオリジナル画像で補足する。
- 校正・校閲の徹底:誤字脱字をなくし、誰が読んでも理解しやすい平易な文章を心がける。
● 技術的・内部SEOの強化(サイト構造や技術面の改善)
- 内部リンク構造の最適化:関連性の高い記事同士を内部リンクでつなぎ、トピッククラスターを形成する。
- 具体的なアンカーテキスト:内部リンクの文言を「こちら」ではなく、「〇〇の詳しい方法」のように具体的にする。
- XMLサイトマップの整備:サイトマップを最新の状態に保ち、検索エンジンにサイト構造を正しく伝える。
- ページ表示速度の改善:画像の圧縮や不要なスクリプトの削除などを行い、Core Web Vitalsの指標を改善する。
- モバイルフレンドリーの徹底:スマートフォンでの表示崩れや操作性の問題を解消する。
- 常時SSL化(HTTPS):サイト全体のセキュリティを確保し、ユーザーと検索エンジンからの信頼を得る。
- 構造化データの活用:FAQ以外にも、記事、製品、イベントなど、コンテンツの種類に応じた構造化データを積極的に利用する。
- URL・メタ情報の最適化:URLは簡潔で分かりやすくし、タイトルやディスクリプションはクリックしたくなる魅力的なものにする。
- 外部リンクの品質管理:リンク切れや低品質なサイトへの発リンクがないか定期的にチェックする。
- 定期的な技術監査の実施:Google Search Consoleなどを活用し、クロールエラーなどの技術的な問題がないか監視する。
● ユーザーエクスペリエンス&CTA改善(訪問者を惹きつけ行動を促す)
- 魅力的な導入文:読者の課題に共感したり、意外なデータを提示したりして、冒頭で心を掴む。
- 文脈に沿ったCTA設置:記事の途中に、その文脈に合った次のステップへのリンク(CTA)を自然に配置する。
- CTAのデザインテスト:ボタンの色、形、文言などをA/Bテストし、よりクリックされやすいデザインを探す。
- 多様なCTAの提供:「問い合わせ」のようなハードなCTAだけでなく、「関連記事を読む」「資料請求」など複数の選択肢を用意する。
- インタラクティブ要素の導入:診断ツール、見積もりシミュレーター、クイズなど、ユーザーが参加できるコンテンツを用意する。
- ランディングページの最適化:CTAをクリックした先のページ(LP)が、ユーザーの期待に応える内容になっているか確認・改善する。
- 社会的証明の活用:顧客の声、レビュー、導入事例などを掲載し、信頼性を高める。
- 運営者情報の明記:「誰が」発信している情報なのか、著者情報や企業情報を明確にし、信頼性(E-E-A-T)を高める。
- 自社サイトのAI要約を検証:AIチャットに自社や製品について質問し、どのように紹介されるかを確認。意図しない回答ならコンテンツ修正のヒントにする。
- 滞在時間・離脱率の分析:Googleアナリティクスでユーザー行動を分析し、満足度が低いページを改善する。
- 質の高い被リンクの獲得:権威あるサイトや関連業界のメディアから自然な形で言及されることを目指す。
- ブランド指名検索の増加:SNS、プレスリリース、イベント登壇などを通じてブランドの認知度を高め、「会社名」での検索を増やす。
- 第三者レビューサイトでの評価向上:業界専門のレビューサイトやGoogleビジネスプロフィールで、良い口コミを増やす努力をする。
- 公共性の高い情報源への登録:Wikipediaや業界団体の名鑑などに、正確な自社情報が掲載されるよう働きかける。
- ナレッジパネルの最適化:Googleビジネスプロフィール情報を充実させ、ブランド検索時にナレッジパネルが表示されるようにする。
- Q&Aサイトでの専門家としての活動:専門分野に関するQ&Aサイトで、権威ある回答者として貢献し、認知を広げる。
- AIと検索の動向を常に追う:Googleの公式発表や業界ニュースをチェックし、新しい機能にいち早く対応する。
- パフォーマンスの定点観測:検索順位やトラフィックの変化を定期的にレポーティングし、データに基づいて次の施策を決定する。
- チーム全体のSEO/AIOリテラシー向上:コンテンツ制作者や開発者など、関係者全員が最新の最適化の考え方を共有する。
- 「ユーザーファースト」への回帰:最後に、全ての施策が「ユーザーにとって本当に価値があるか?」という原点に立ち返って見直す。
ol>
● オフサイト対策と継続的改善(サイト外の評価向上と追跡)
まとめ:変化を恐れず、本質的な価値提供へ
HubSpotの事例は、SEOというゲームのルールが大きく変わろうとしていることを示す象徴的な出来事です。 [20] これまでの「検索エンジンをハックする」ようなテクニックはもはや通用せず、AIとユーザーの両方から「信頼できる専門家」として認められることが、これまで以上に重要になります。 [13, 26, 27]
今回紹介した50のチェックリストは、決して小手先のテクニックではありません。その多くは、「ユーザーに対して、より誠実に、より分かりやすく、より価値のある情報を提供する」という、マーケティングの王道に立ち返るためのものです。 [22] AIの台頭は脅威ではなく、コンテンツの本質的な価値が問われる良い機会と捉えるべきです。
トラフィックの「数」だけを追い求める時代は終わりを告げようとしています。これからは、自社のビジネスに本当に貢献してくれる「質」の高いユーザーと、いかにして深い関係を築くかが問われます。本記事のチェックリストを参考に、ぜひAI時代を生き抜くためのウェブ戦略へとアップデートしてください。