生成AI と著作権:日本の法改正案を弁護士が読み解く
ChatGPT や Midjourney のような 生成AI は、一瞬で文章や画像を生み出す便利なツールですが、作品をつくる裏側では「誰の権利がどう守られるのか」という難題が横たわっています。本記事では、2024〜2025 年に文化庁がまとめた 最新の法改正案 をベースに、よくある疑問を Q&A 形式 で整理し、ビジネスパーソンが知っておくべきポイントをやさしく解説します。

Q1. そもそも生成AIと著作権の何が問題?
生成AI は過去の作品を大量に学習して新しいコンテンツを生み出します。
・学習データ に他人の著作物を無断で使っていないか?
・AI が作った作品の権利帰属 は誰のものか?
・既存作品に似すぎたアウトプット は侵害にならないか?
こうした論点がクリエイター、企業、一般ユーザーの間で急浮上しています。
Q2. 現行法のキモ ― 著作権法「第30条の4」とは?
日本の著作権法は 2018 年改正で 柔軟な権利制限規定(第30条の4)を導入。
ポイント:
① 「鑑賞目的でない利用」 なら、著作物を学習データに使っても原則許諾不要。
② ただし 権利者の利益を不当に害する 場合は適用外(有料 DB を勝手にコピー等)。
③ robots.txt など 技術的制限 を破って収集したデータも適用外となる可能性。
Q3. 2024 年の「AIと著作権に関する考え方」報告書は何が変わった?
文化庁は 2024 年 3 月、生成AI の課題を整理した報告書を公表しました。主な示唆は次の 3 つ。
- 第30条の4 の解釈を 学習目的にも適用 する方針を明示
- AI 生成物 は 人間の創作的関与 がない限り著作権が発生しない
- 著作権侵害リスク(酷似アウトプット等)への対策を事業者・ユーザー双方に提示
Q4. 学習データに他人の作品を使っても本当に大丈夫?
結論:通常の「まとめて機械学習」 は許されやすいが、次のケースは要注意。
- 特定作家の絵柄だけを再現する目的で集中的に学習 → 鑑賞目的と評価される可能性
- 有料コンテンツを購読せずにスクレイピング → 市場を奪い権利者利益を害する
- robots.txt で拒否されているサイトをクロール → 技術的制限を無視
Q5. AI が作った作品に著作権はある?誰のもの?
AI が完全自動で作ったデータ には原則著作権なし=パブリックドメイン扱い。
ただしユーザーが
- 詳細なプロンプトで表現上の工夫 を指示
- 生成結果を取捨選択・編集 して完成形に仕上げた
など 創作的関与 が認められれば、その人に著作権が発生します。
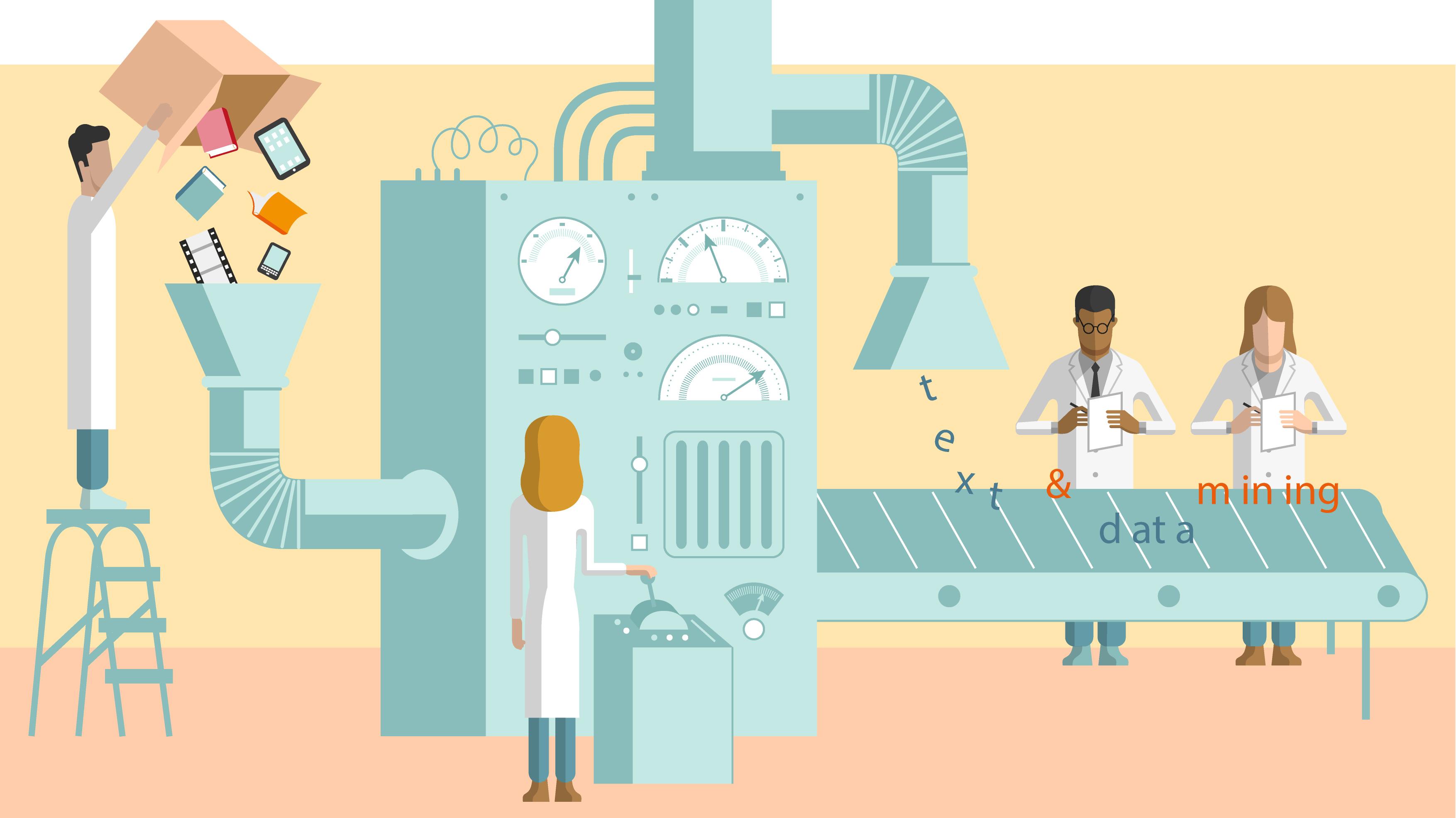
Q6. 「似すぎ」はアウト?作風を真似するのはセーフ?
著作権が守るのは 具体的な表現。
・作風(スタイル) はアイデアの範囲 → セーフ。
・特定作品をほぼ再現 → 類似性+依拠性 があると複製・翻案権の侵害。
例:2024 年中国・広州の「ウルトラマン画像」判決では、AI 事業者に削除命令と賠償が下されました。
Q7. 権利者・AI企業・ユーザーの主張を整理
| 立場 | 主な主張・懸念 |
|---|---|
| 権利者 | 無断学習・酷似生成は困る。許諾制や補償金を検討してほしい。 |
| AI企業 | 過度な規制は国際競争力を削ぐ。オプトアウトなど自主対策で対応。 |
| ユーザー | 法律リスクが分かりにくい。政府・事業者の明確なガイドが欲しい。 |
Q8. 具体的なトラブル事例
- 国内イラスト投稿サイトで AI 作品が「自作詐称」→ サイト側が AI 作品の明示ルール導入
- 広州ウルトラマン判決(2024)→ 事業者に 30 万元賠償+生成停止命令
- 米 Thaler 事件(2025)→ 「AI のみ生成」は著作権登録不可と控訴裁が確定

Q9. ビジネスパーソンが取るべき 5 つの実践策
- 利用規約とガイドライン を確認(商用可否・帰属条件)
- 機微なデータは自前データ で追加学習し、外部データは要出典確認
- 公開前に類似検索 で既存作品との酷似をチェック
- 自社作品を守るなら robots.txt やウォーターマークでオプトアウト意思を表示
- 契約書 で権利帰属を明確化し、責任範囲を事前に定める
まとめ
生成AI はクリエイティブの可能性を広げる一方、権利侵害の火種 も抱えています。2024 年の文化庁報告書は「現行法でも一定の対応は可能」としつつ、判例の蓄積を見て 法改正を検討 と明言しました。今後の議論次第でルールは変わる可能性があります。
最新情報をキャッチアップしつつ、リスクを抑えて AI を活用 しましょう。


